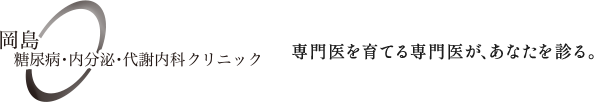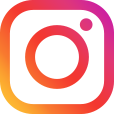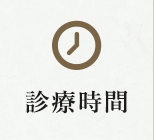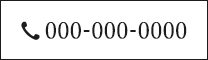血圧とは
 血圧は、心臓から押し出された血液による血管壁への圧力のことで、心臓が収縮した際には最も高くなり(収縮期血圧)、静脈からの血液を心臓が受け取る際には心臓が拡張して最も低くなります(拡張期血圧)。血圧測定では、収縮期血圧と拡張期血圧の両方を計測して記録します。
血圧は、心臓から押し出された血液による血管壁への圧力のことで、心臓が収縮した際には最も高くなり(収縮期血圧)、静脈からの血液を心臓が受け取る際には心臓が拡張して最も低くなります(拡張期血圧)。血圧測定では、収縮期血圧と拡張期血圧の両方を計測して記録します。
高血圧の定義
血圧が高い状態が続いていると確認できる場合に高血圧症と診断されます。血圧はちょっとした動作や緊張などで変動しやすいため、安静時に計測します。ご自宅で計測した家庭血圧に比べ、医療機関で計測する診療室血圧は高めに出やすい傾向があり、高血圧と定義される値も区別されています。
高血圧と定義される血圧
診察室血圧:収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上
家庭血圧:収縮期血圧が135mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上
世界中で上記の基準が使われていますが、米国だけは欧米の疫学調査に基づいた研究により高血圧の定義を130/80mmHg以上としています。
血圧が高い状態が続くと血管に大きな負担がかかり続け、動脈硬化や脳出血をはじめとした数多くの疾患の発症・進行リスクが上昇します。血圧を正常範囲に保つ治療を受けて適切にコントロールできれば、心筋梗塞、心房細動、大動脈瘤、脳卒中などの発症リスクを低減できます。
高血圧治療の目標血圧
高血圧で最も懸念されるのは、心筋梗塞や脳卒中などの原因となる動脈硬化の発症や進行ですが、他にも全身の様々な血管や毛細血管を含む組織や臓器にダメージを与える可能性があります。こうした疾患の発症・進行リスクを抑制するために、正常範囲の血圧を維持することが重要です。
年齢や他の疾患の有無などにより、目標血圧の数値は変わります。日本高血圧学会『高血圧治療ガイドライン2019』では下記のように定めていますが、ガイドラインではさらに細かな目標の調整が注記されており、実際にはそれにきめ細かく合わせた目標の調整が必要となります。主治医と相談して適切な目標値を決めましょう。
| 診察室血圧 | 家庭血圧 | |
|---|---|---|
| 75歳未満の成人 脳血管障害がある 冠動脈疾患がある(両側頚動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞がない) 慢性腎臓病(CKD)がある(タンパク尿陽性) 糖尿病がある 抗血栓薬服用中 |
130/80mmHg未満 | 125/75mmHg未満 |
| 75歳以上の高齢者 脳血管障害がある(両側頚動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞がある、または未評価) 慢性腎臓病(CKD)患者の方(タンパク尿陰性) |
140/90mmHg未満 | 135/85mmHg未満 |
高血圧の原因
遺伝的な背景があり、生活習慣が関与して発症する本態性高血圧症と、他の疾患の症状として高血圧を起こしている二次性高血圧症に分けられます。二次性高血圧症の主な原因疾患には、原発性アルドステロン症、腎血管性高血圧症や褐色細胞腫などがあります。日本では高血圧症の9割が本態性高血圧症が占めていますが、約10人に1人の割合で存在する二次性高血圧症の場合には原因疾患の適切な治療を行わないと高血圧治療だけでは十分な改善効果を得られません。
なお、どちらの場合も高血圧自体にはほとんど自覚症状がありません。健康診断で高血圧を指摘された場合や、ご自宅で血圧を測って高めの場合には、できるだけ早めに受診してください。
高血圧の治療
二次性高血圧症の場合は原因疾患の治療を行います。精密検査や外科的治療など当院で対応できない場合は連携施設である山梨大学附属病院糖尿病・内分泌内科等へ紹介させていただきます。
本態性高血圧の場合には、基本的に食事療法と運動療法を行いますが、状態などにより薬物療法を併用して目標血圧を維持できるようにします。食事療法と運動療法による生活習慣改善は、継続できなければ意味がありませんので、当クリニックでは患者様と相談し、できるだけストレスなく続けられる方法を一緒に探しています。
生活習慣の改善
減塩
日本人は世界的に見ても塩分摂取量が多く、減塩に取り組むことで血圧が改善しやすい傾向があります。塩・味噌・醤油・ドレッシング・ソースなどの調味料に加え、ハム・ベーコン・ソーセージ、干物、漬物などの加工食品、インスタント食品など、塩分の多いものをできるだけ控えるようにしましょう。加工食品のパッケージには必ず成分表が記載されていますので、買い物の際には「食塩相当量」を確認しましょう。1食で1日の摂取量の目安である6gを超えてしまうものもありますので、必ず確認してください。
減塩しても食の楽しみを損ねないためには、旨味の強い出汁を使う、酸味や甘味で味に変化をつける、薬味・スパイス・ハーブで香りや風味をプラスするなどが有効です。
ダイエット・肥満予防
 大規模な調査により最も病気になりにくい適正体重がわかっています。適正体重は身長によって変わり、現在の体重が適正かどうかは体格指数(BMI)を算出することで判断できます。
大規模な調査により最も病気になりにくい適正体重がわかっています。適正体重は身長によって変わり、現在の体重が適正かどうかは体格指数(BMI)を算出することで判断できます。
BMI=体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)}
適正体重 BMI=22.0
低体重と肥満の場合は、どちらも様々な病気の発症・進行リスクが適正体重に比べ高くなります。
肥満している場合は、生活習慣病を発症しやすい傾向があり、適正体重を維持することが生活習慣病の改善に役立ちます。カロリーコントロールと適切な運動を習慣的に行って減量しましょう。
ただし、過激なダイエットを行うと貧血や生理不順などを起こすリスクがあり、リバウンドもしやすくなってしまいます。また、他の疾患がある場合には食事制限の内容が変わる場合もあります。必ず医師と相談してから行うようにしてください。
| 低体重 | BMI18.5未満 |
|---|---|
| 普通体重 | BMI18.5~25.0 |
| 肥満 | BMI25.0以上 |
減酒・禁酒
1日あたりの適切な飲酒量は、男性では純アルコールで20gとされ、ビールは500mL、日本酒は1合、ワインはグラス2杯、ウイスキーはダブル1杯 が目安となります。女性はアルコールの影響を受けやすい傾向があり、分解にも時間がかかりますので、男性の半量程度が目安となります。1日飲まなかったから次の日は倍飲んでいいということではなく、月に1回の飲酒でも適切な飲酒量は変わりません。
運動
軽い有酸素運動を続けることは、減量にも有効ですが、血流の改善、血管など循環器をはじめとした全身の健康にも大きく役立ちます。激しい運動は必要なく、早足で30分程度散歩し、週に何度か筋肉トレーニングを行うことをお勧めしています。筋力がアップすると代謝も上がり、減量効果も得やすくなります。
ただし、状態や合併症の内容などによって、運動に制限が生じる場合もありますので、必ず医師と相談してから行うようにしてください。
禁煙
ニコチンは血管を収縮させて血圧を上昇させますので、禁煙が必要です。また、喫煙していると、厳しい食事制限や運動療法を行っても十分な効果を得られません。呼吸器疾患や循環器疾患、様々ながんのリスクを下げるためにも禁煙は有効です。